元読者3人からなる「月刊OUT勝手連」が、当時の編集部員やライターなど、雑誌にかかわった方たちへのインタビューを通して、18年にわたる雑誌の歴史を振り返ります。
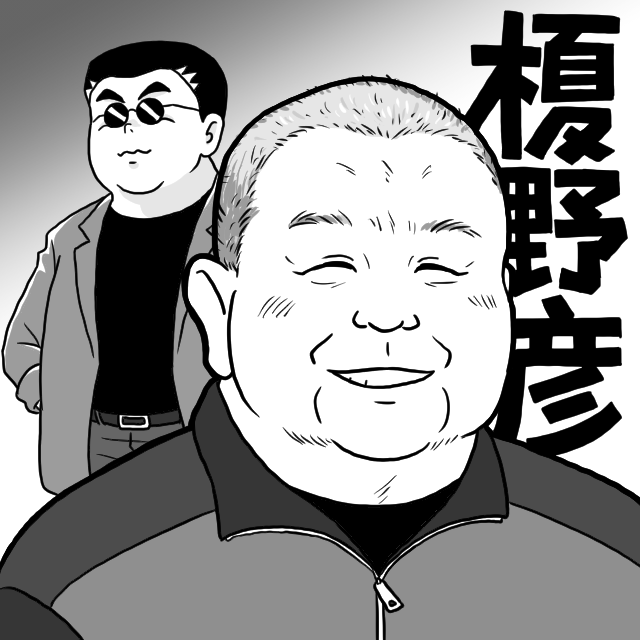 略歴
略歴1958年生まれ。実兄であるOUT編集者のRⅡ氏をきっかけに、月刊OUTにライターとして参加。1998年『時空のクロス・ロード ピクニックは終末に』にてライトノベル作家デビュー、鷹見一幸のペンネームで『でたまか(アウトニア王国物語)シリーズ』など著作多数。
(聞き手:OUT勝手連 SII/KN/WH、 イラスト:小野秀一)
インタビュー:2025年2月22日
公開日:2025年8月25日
兄貴が死んでちょうど10年か。2014年の12月2日だからね。あの時まだ60だったからな。俺なんかもう67だよ。この1月25日で67になっちゃったよ。兄貴の寿命を7年も先行っちゃったな。
なんでOUTに関わったかってことから始めるとね。いちばんキーになってるのは、Cさん[1]だった。これはすごく大きい。俺も兄貴も両方とも。実は、Cさんと兄貴は同じ高校(韮山高校)の同じクラスで、CさんはSF研究会みたいなのをやってたのよ。兄貴はブラスバンドの部長をやってたんだけど、すごいSFマニアだったから、俺も一緒だけど、SFについて深い繋がりがあって仲が良かった。

俺が中学3年で、兄貴が高校生の頃かな。お年玉でもらったお金を持ってね、俺と兄貴とで神保町に来て、2人で手分けして買って、リュックサックにSFの古本がっつり詰めて、静岡の三島まで帰った覚えがあるよ。帰りの電車の中で2人でがーって読んで。
それはもう、最高に楽しいですね。
兄貴は京都立命館大学に行ったんだけど、京都中の古本屋でSFマガジンのバックナンバー集めて、創刊号以外全部持ってた。そんな兄貴が単位を落として卒論を書けなくなった時に、Cさんはみのり書房と同じような会社に勤めてたの。ちょうどOUTがアニメやり始めた時で、アニメとかSFとかそういうので書ける人間いないかって、おそらくCさんのところに話があって、だったら木戸岡はどうだって、兄貴が呼ばれた。だから、Cさんがいなけりゃ、俺も兄貴もOUTには関わらなかった。
アニメージュ[2]が創刊される直前、OUTがヤマトの特集で馬鹿みたいに売れて、雑誌でありながら増販増刷かかるっていう状態になった。その後しばらくOUTの方もいろいろ試行錯誤して、アニメだと売れるってのはわかり出したんだろうな。
そのころアニメのファンとかマニアってのは、女の子が多かったんだよ。うちのカミさんは名古屋出身なんだけど、『海のトリトン』[3]の上映会を女の子連中が集まってやって、名古屋テレビにみんなで再放送お願いしますってハガキをガンガン出して、それで再放送になったりして。
第2回〜第3回コミケあたりまで遡るんだけど、もうとにかく女の子が多くてびっくりしたね。当時、萩尾望都さん[4]とか、『ボルテスⅤ』[5]のハイネル様とか長浜さん[6]のラインがちょうど来ていたころで、開場前に階段のところでラジカセでボルテスの曲をかけてる女子高生がいたのよ。すげえなと思って。
後になってからOUT編集部で「俺、コミケに初めて行った時そういうのがいてね」つったら、浪花愛さんが「あ、それ私」って(一同爆笑)。
あの頃、だからそうやってファンっていうのはいっぱいいたし、アニメファン・漫画ファンってのはいたけど、それを商売にできる人間ちゅうのがいなかったんだね。
研究会とかさ、好きなのはいるんだよ。じゃあ「どういう風に面白い」というのを、分析してちゃんと文章にして書ける人間がいるかっていうと、それはすごい差があるの。読ませる文章と、自分の好きな文章は違うからね。作家でもそうなんだけどさ、書きたい文章と書ける文章は違うから。そうするとね、いないんだよ。どの出版社にもいない。それで、アニメージュが引っ張ってきたのが早稲田大学のアニメ研の連中で、これが花小金井[7]だよな(笑)。
その当時そういう人間がいて、実力がどんなもんかわからん、とりあえずやらせてみろっていう感じで、本当に創成期だね。海のものとも山のものともわからん人間が、いきなり雑誌のコラムを任されてやれるかって。「とにかく書け」っつって、いきなり原稿用紙をペラッと渡されて、
「じゃ、これちょっとまとめて書いてくんない?」
「どこで書きゃいいんですか?」
「そこのカウンターで書いて」
って言われて、立ってカウンターで文章書いてるとか、そういう時代だった。
ましてOUTなんてすごいちっちゃい出版社でしょ。で、それで兄貴が引っ張りこまれて、画面の構成とかいろいろやり始めて。そしたら、やっぱり知識量が違う。普通じゃないのよ。だから、こいつはすごいってことになって、Cさんの方から大徳さんに行って、入社試験っていったら、
「名前なんですか」
「木戸岡和典です」
「お父さん、何してますか」
「家で仕事をしています」
「はい採用」
っていう冗談があるんだけど、ほとんどなし崩しに編集部に入ってる。
当時、俺は警察官をやってたんだけど、高校時代からみなもと太郎さん[8]とか聖悠紀さん[9]の『作画グループ』[10]に入ってて、そっちの繋がりもあったの。で、みなもとさんの仕事場に行ったりして遊んでた。でもアニメなんて、警察で仕事してる連中には全く話が通じないわけよ。警察官でアニメ好きなんていないから。まだ宮崎事件[11]の前だけどね。そうすると完全に孤独なの。
それが作画グループの仕事場に遊びに行くとそういう話ができるでしょ。そういう話しかしないじゃん。すごい楽しかったのね。そうすると、最初はもう初対面で、向こうは大先生だからただのファンだなと思ったんだろうけど、いろんな話をしてるうちに、聖さんやみなもとさんにも、こいつ面白いなと思ってもらえたんだと思う。
また遊びに来なよって言われて行ったら、いきなりみなもとさんから、「次の週刊平凡パンチのアイデア、何がある?」って言われて。「私なんですか?」つったら、「ネタいっぱい持ってんじゃん。いろいろ出してみなよ」って言われた。当時、平凡パンチに3〜4ページとかで連載持ってたみなもとさんのネタ出しやらされて。まだ21〜22の頃だよね。
いきなりそれやられて「あ、面白いな」と思ったんだよ。こういうバカっ話はいっぱいやってたのよ。もともと落語は大好きだったしね。バカ話のネタでパロディネタみたいなこともやってたから、そういうのが作画グループでウケた。それをプロの先生にアイデアとしてウケたっていうことがすごい自信になったね。
でもそこから終わって帰ってくると、激務が待ってるわけ。3日に1度24時間勤務だから、朝8時半に出勤したら、次の日は朝8時半までの仕事。途中でいちおう4時間仮眠はあるんだけど、ないようなもんだよね。何か事件があったら、仮眠時間だから寝てますとは言えないから。もう完徹なの。その代わり、帰ってくるとその日は明け番で、次の日まで休み。うまく明け番と休みっていうのが繋がると、その日と次の日まるまる1日休みになるの。そうすると1泊2日で時間ができる。
この時間、平日はどこ行ったってやってないし、やることないからただ本読んでるんだけどね。そうすると、作画グループの漫画家の先生のとこへ電話して…「ちょっと忙しいから」って言われたらダメだけど、「あ、いいよ、遊びに来なよ」とか言われたら、行くでしょ。それで1日、アシスタント連中のなかで夕方夜中までバカっ話して帰ってくるの。
みなもとさんとか聖さん…それから沢田ユキオさん[12]って、コロコロコミックで『スーパーマリオくん』描いた人だけど、この人は最高の人だった。沢田さんの仕事場は早稲田の6畳1間みたいなとこでさ、そこへ当時、作画グループの若手が5、6人ゴロゴロしてた。ひどい時には、沢田さんが打ち合わせに行っていない時に「ちょっと留守番しててくれ」って言われて俺がいたら、仲間内が集まってきて、いきなりビール買い込んできて。そこへ沢田さんが帰ってきて、「お前ら何やってんだ」って怒られたりね。
すごく初期のOUTで、『超人ロック』の特集('77年12月号)の時に作画グループの人がいろいろ漫画描いたりしてますが、その頃にはもう出入りされてたんですか?
うん、OUT増刊のランデヴーで『超人ロック』の連載が始まる頃に、もうすでに聖さんのところに遊びに行ってた。
だからあの当時、梁山泊みたいなもんだったんだよ、あのへんは。形ができる前のカオスな状態がぐるぐるしちゃってた。ゆうきまさみさん[13]に聞いた時も、そういう感じだったらしいよね、江古田のまんが画廊[14]とか。ああいうものが、おそらく都内にいっぱいあったと思う。
その「作画グループ」系列の知り合いで漫画家の宇多川さんって人がいて、メカ・軍事関係を描けるからっていうんで、青池保子さん[15]の『エロイカより愛をこめて』を手伝ってたんだけど、あの中でエーベルバッハ少佐が、当時誰も知らない『パンツァーリート』を歌うシーンがあるんだよ[16]。その歌詞の翻訳をウダさんと俺がやった。
翻訳ですか?
うん、ドイツ語をそのまま書くわけにはいかないから、日本語に訳さなきゃいけない。「我が戦車はごろごろと 疾風の中をつき進む」とか、そういう日本語歌詞にしたと思う。
そんな感じで、ときどき変なところで名前と顔が出て、呼ばれたりすんのよ。
一時期、警察の中で聞いたりした怪談話をやってたのよ。竹宮恵子さん[17]の「トランキライザープロダクト」[18]っていうところのアシスタント仲間から「今度もしよかったら、一席お願いします」って呼ばれた。別に俺は芸人でもなんでもねえんだけどって言いながら遊びに行った。そしたら少女漫画家さんのアシスタントたちにすごく受けてね。そのあと、怪異とか変なことが起こると、「幽霊が新しく来た」つってパーティーに呼び出されてた(笑)。
一条ゆかりさん[19]とこでは、仕事が忙しくて全然乗れていなかったミニクーパーのバッテリーが上がってエンジンがかからないって。よせばいいのに「押しがけしたら、かかるんじゃないですか?」なんて話したんだよ。当時、一条さんの仕事場って、坂道のずっと上の方にあったの。この坂を下ってる途中に押しがけやって、アクセルを踏んで、クラッチ繋げば、エンジンかかんじゃないかって。…馬鹿だよねえ。「面白い」ってやって見たら、かからなかった(笑)。そのあとハッと気がついて「またこれ押して戻らなきゃいけないのか!」
そこまで誰も気がついてなかった。真夜中の坂道をさ、延々ミニクーパーを押して登ってったよ。そういう馬鹿なことばっかりやってた。
それから俺の話じゃないんだけど、某○○って漫画家(編注:誰もが知る人気作家です)がぜんぜん売れなかったころに、練馬の仕事場でひとりで一生懸命頑張ってたんだけど、どうしてもお金がなくて、お腹が空いて、隣が大家さんのキャベツ畑。夜中にそっとキャベツ盗んじゃったんだって。そしたらばれて、大家さんが来てね、
「お腹が空いたらいつでもとっていいから」って言われた。
「あんた律儀だから、キャベツ半分だけ食べて、半分戻されても困るから」って。
(一同爆笑)
それも本当に落語みたい。
そういう落語みたいなネタの話、実際にやってたからね。
そういうカオスな時代。実は一条ゆかりさんのところに聖悠紀さんがアシスタントに行ってるのよ。ちょっと未来的なシーンやメカのシーンで聖さんが描いてる。だからそういう関係で
変な繋がりがあって。でも当時、そういう時にはみんなには警察官ってことは黙ってたの。
わけのわからない面白い人っていう感じだったと。
月刊OUTで仕事始めたのは、そのちょっと後だよね。だからOUTで仕事し始めた時にいろんなところに行っても、繋がりがあって知ってたから、楽は楽だったけどね。まさかみんなもほんとに俺が警察官なんて知らなかったんだろうな。
そうやってるうちに、兄貴がOUTに入ったっていうんで。おや、これはすごいなって。聖先生だったかな。
「月刊OUTに木戸岡って人がいたけど、知り合い?」
「・・・兄貴です」
「なんだよ、そうか」
なんて。珍しい名前だからね、木戸岡なんて。
それで兄貴んとこに遊びに行ったのよ。当時は『ミックスサンド』だったかな。
「ハガキ選ぶの、大変だからお前やれ」
「俺のセンスでいいの?」
「いや、別に構わんよ」
って言われて、それでやって。で、バカ話してたら、大徳さんとかが「お前うるせえぞ」って。あと、Gさんかな。「もううるさくて仕事になんない!」ってキレられたがことあった。
そうこうするうちに、大徳さんかな、Cさんだったかな、「口で言ったってしょうがないからネタを書いてきなさいよ」って言われたんだよな。それで面白がって書いてみた。最初なんて原稿用紙じゃないよ、レポート用紙みたいのにさ。だって当時は小説なんて書いたことないしね。
何やったかっていうと、漫画の元になるコンテなわけ。そのコンテのやり方に「セリフだけを書き出す」ってのがあったのね。「画面の割り付けの”レイアウト”とは別に、会話のテンポの良さっていうのがすごく大事だ」っていろいろ先生から教わって。ぽんぽんぽんぽん会話のパターンが続けば、面白ければ読者は先を読んでくれるから、構図もいいけども、ネームが大事だってな。
それで会話形式のネームをバーっと書いて持ってったら、もう大受けだったんだよ。ただ、「でも、この調子じゃ載せられないな」っていうんだけど、その時にバイトで来てた花小金井が腹抱えて笑っててさ。
大徳 「花小金井くん、これ小説にできる?」
花小金井 「やってみます」
大徳 「でもうちは本誌には載せられないか、すごい長いから」
C 「うちでアニパロココミックスやるから、じゃあそれに載せよう」
って話でいきなりデビューしたのが、1982年の『大いなる挑戦』ってやつ。
なんせ挿絵がゆうきまさみだから。「『締め切りを守らぬ漫画家だ』って自分が殺されて吊るされるシーンを書くのは嫌ですね」ってゆうきさんが話してたのを、後で聞いたら覚えてた。これがおそらく俺の商業誌のデビューだよね。
ただ、原稿料をもらうわけにはいかないから兄貴の名前にしたんだけど、編集部員が書いたものは原稿料は出ない。それじゃまずいからってんで、映画の試写会の券とかそういうのを山ほどもらってね。東宝の本社とか試写室に行ってタダで映画を山ほど見てきた。だから、本当にあのころは映画ばっか見まくった。
公務員だからお金もらえないので、お金の代わりにそれが原稿料だった、と。
最初はCさんとのやり取りだったんだけど、そうこうするうちにCさんの方でもそう度々はやれないからって今度は本誌で…大徳さんが色気を出したのかな。OUTの本誌でやらないかって。ただその時、OUTの本誌にアニパロ小説が載ってたんだよね。『ムーミン谷の赤い彗星』[20]みたいな。
留止(るしい)さんですね。
忙しくなったとかで辞めるって話だったと思うんだよ、確か。それで、
大徳「代わりに、キミやんないか」
榎 「いや俺、小説は書いたことないですよ」
大徳「大丈夫。花小金井つけるから」
それでまあ、俺がセリフだけ書き出し、キャラクターと名前…ト書きだよね。誰が何を喋ったっていうのを書き出して、それを花小金井に渡して、花小金井がそれを小説化する。
で、花小金井が「加筆していいですか?」って言うから
榎 「うちは2人で合作なんだから、面白いと思ったら、どんどん加筆しちゃってよ」
つったら、花小金井がどんどん加筆するんだよ。それがまた妙におかしいんだよ。そしたら「徹くんのも面白いけど、花小金井くんが書いてきたのも、なんか妙で面白いね」って、大徳さんが両手をあげて賛成してくれて、それでOUTの連載っていう形になったんだ。
花小金井は電話で打ち合わせするときにあいつからかけてくるんだけど、あいつ電話引いてなくてさ。大家さんに許可もらって下宿のピンク電話を自分の部屋に引き込んで、十円玉を山積みにして打ち合わせをしてた。そういう時代だった。
[1] Cさん : Cさんこと、杉本幸彦氏は元月刊OUT編集部員、後に『アニパロコミックス』編集長。OUTでは投稿コーナー『ミックスサンド』などを担当した。
[2] アニメージュ : 徳間書店から発刊されたアニメ専門誌。'78年5月26日創刊(7月号)。創刊号の表紙は『宇宙戦艦ヤマト』。
[3] 海のトリトン : 手塚治虫の漫画(青いトリトン)。アニメ版は'72年、朝日フィルム制作、監督は富野喜幸。日本で初めてファン主体のテレビアニメのファンクラブが作られたとも言われる。'79年11月号の記事中に「ファントーシュ」の広瀬和好の証言が紹介されており、大阪から東京のスタジオに通っていた一人の少女ファンがファンクラブをつくり、それがあっという間に全国に広がっていったとのこと。
[4] 萩尾望都 : 漫画家。代表作に『ポーの一族』『トーマの心臓』『11人いる!』など。竹宮恵子・大島弓子・山岸凉子らと共に「花の24年組」と呼ばれた。
[5] 超電磁マシーン ボルテスV : 長浜忠夫監督・創映社制作のロボットアニメ。'77年-’78年。プリンス・ハイネルは敵側の若い美形の貴族。当時フィリピンで大人気となり、2023年には『ボルテスV レガシー』としてフィリピンで実写化された。
[6] 長浜忠夫 : アニメ監督。一連のロボットアニメ(『コン・バトラーV』『ボルテスV』『闘将ダイモス』)は長浜アニメと呼ばれ、そのドラマ性・演出は後に大きな影響を与えた。’80年に逝去。月刊OUTではインタビューや本人のエッセイのほか、’81年12月号では一周忌特別座談会が掲載されている。
[7] 花小金井和典 : ライター。'80年代中頃にアニメ記事や、榎野彦との合作(原作:榎野彦 潤色:花小金井和典)による数々のアニパロ小説を手がける。投稿コーナー『花小金井かんとりいくらぶ』('85-'88年)は人気を集めた。
[8] みなもと太郎 : 漫画家。代表作に『ホモホモ7』『風雲児たち』など。2021年逝去。
[9] 聖悠紀 : 漫画家。代表作『超人ロック』は'67年から50年以上にわたって掲載誌を転々としながら描き継がれた。OUTで'77年12月号にて特集されるが、それ以前は同人誌と貸本向けの単行本での発表であった。初の商業誌連載は'78年、OUT別冊『ランデヴー』にて。その後、'91年9月号よりOUTにて「聖者の涙」編を連載。
[10] 作画グループ : 会員制同人誌サークル。会員にはプロの漫画家が多いが、漫画が好きでさえあれば誰でも入れるオープンな会だった。初期のOUTには作画グループの広告がよく載っていた。
[11] 宮崎事件 : 89年に首都圏で起きた連続幼女誘拐殺人事件。犯人(宮崎勤)の部屋に多数のアニメ作品の録画ビデオテープがあったことなどから、社会的にいわゆるおたく・ロリコンへのバッシングが生じた。この部屋の模様が報じられた際にエロコミックと並んで月刊OUTの表紙が映っていた。SIIがOUT編集部に見学に行った折に、NHKの社会部から電話がかかってきた場に居合わせたことがある。
[12] 沢田ユキオ : 漫画家。'90年より月刊コロコロコミックなどに『スーパーマリオくん』を長期連載する。単行本は既刊60巻(2025年7月現在)。
[13] ゆうきまさみ : 漫画家。代表作に『究極超人あ〜る』『機動警察パトレイバー』『新九郎、奔る!』など。デビューの経緯が月刊OUTに掲載されたアニパロ作品『ざ・ライバル』(ただし4Pのうち最初と最後のページだけ)であったのは有名。
[14] まんが画廊 : 76年から'80年まで江古田に存在した喫茶店。漫画・アニメの業界人やファンが出入りしており、ゆうきまさみも川村万梨阿やとまとあきとこの店で知り合う。
[15] 青池保子 : 漫画家。代表作に『エロイカより愛をこめて』『アルカサル-王城-』『ケルン市警オド』など。
[16] パンツァーリート : 1933年に作られたドイツの行進歌。このシーンは『エロイカより愛をこめて』1巻No.2に掲載されている。「当時誰も知らない」と表現しているのはアニメ『ガールズ&パンツァー』の挿入歌として使用されたことで認知度が上がったことを踏まえていると思われる。 Wikipedia
[17] 竹宮恵子 : 漫画家。代表作に『風と木の詩』『地球へ…』など。のちに「竹宮惠子」に表記を変更。少女漫画界において「24年組」と呼ばれる一人。OUTでは'79年1月号で竹宮恵子特集、'80年5月号にひおあきらとの対談が掲載されている。
[18] トランキライザープロダクト : 竹宮惠子氏の著作権を預かり、運営する有限会社。2013年までは鎌倉市にあったが現在は福岡県に。 リンク
[19] 一条ゆかり : 漫画家。代表作に『デザイナー』『砂の城』『有閑倶楽部』『プライド』など。
[20] ムーミン谷の赤い彗星 : 留止(るしい)によるアニパロ小説。'80年11月号掲載。シャアとノンノンが…という悶絶必至の内容。

